再建築不可物件の相続放棄
建て替えできないことから相続するリスクが大きい再建築不可物件。相続放棄をすることも選択肢のひとつとしては考えられますが、状況次第では不動産売却も検討する価値があります。本稿では、再建築不可物件の相続リスクや相続放棄の流れ、注意点などをご紹介します。
再建築不可物件とは

再建築不可物件は、建て替えや増築が不可能な不動産をいいます。主に都市計画法の都市計画区域や、準都市計画区域に点在しています。
再建築不可物件の場所に住宅などが建っている場合、取り壊すと新しい建物を建てることができません。昭和25年の建築基準法の制定によって、緊急車両の円滑な通行や避難時の誘導経路確保を目的とした間口2mの接道義務が生じたことにより、特にそれ以前の古い建物は再建築不可物件のケースが多くなっています。
道路に接していない
土地に建物を建築する場合、その敷地は道路に面している必要があります。つまり、周りを建物に囲まれて道路に接していない土地には建物を建てることはできないということです。「道路に隣接していること」は建物を建てるための最低条件です。
接道路が2m未満
道路に接していればどんな形でもいいのかというとそうではありません。建物を建てられる基準は都市計画法に基づいて定められていて、都市計画区域内や準都市計画区域内の土地の場合は建築基準法上の接道義務を満たす必要があるので注意してください。具体的には幅員が4メートル以上の建築基準法上の道路に対して敷地が2メートル以上接している必要がありますので、1メートル程度しか接していない場合などに建物を建てることはできません。
建築基準法上の道路に接していない
接している道路が「幅員4メートル以上で敷地に2メートル以上接している」という条件を満たしていたとしても、その道路が私道などである場合には建物を建てることができません。敷地に隣接している道路は「建築基準法上の道路」である必要があります。
市街化調整区域にある
これまでに紹介した条件を仮に満たしていたとしても、該当の土地が市街化調整区域にある場合は建物を建てることができません。建物を建てる際にはその土地が市街化調整区域でないことを確認することが重要です。
再建築不可物件を相続するリスク
再建築不可物件を相続する場合、以下のリスクに注意が必要です。
建て替えが不可能
接道義務を満たさない再建築不可物件は、原則として建て替えや増築ができません。既存の建物のリフォーム・リノベーションは可能ですが、増築などは認められないため気をつけましょう。もし建て替える場合、隣地を取得して接道義務を満たすなど、何らかの工夫が求められます。
老朽化や災害で損壊しても再建築不可
現在建っている建物が老朽化したり、災害で損壊した場合も原則建て替えができません。対応策としてリフォームという選択肢がありますが、古い建物の改修は予想以上に費用がかかることが多く、耐震性や断熱性の向上にも多額の費用が必要となるため注意が必要です。
更地にすると固定資産税が増加する
再建築不可物件を更地にした場合、固定資産税が増加する可能性があります。一般的な宅地の場合、固定資産税を軽減する住宅用地の特例が適用されています。しかし、更地にすると特例の適用外となるため、固定資産税が数倍に膨らむリスクがあります。
修繕費などの維持費がかかる
再建築不可物件を維持するには、外壁塗装や壁材の交換、屋根の葺き替えなどの維持費がかかります。長い目で見ると高額になるため、経済的な負担が増えるおそれがあります。負担を減らしたい場合、何らかの手段で手放すことも検討をおすすめします。
損害賠償を請求される恐れがある
再建築不可物件が著しく老朽化している物件である場合などにおいては、解体せずに物件を放置していると常に損害賠償リスクが伴います。具体的には地震や台風などのような自然災害が起こった際、隣家や通行人などの周辺に被害を及ぼす恐れがあるためです。具体的な被害が発生してしまった場合、被害者から損害賠償を請求されるリスクがあります。
再建築不可物件を相続放棄する手続きと流れ
遺言書を確認
まずはじめに確認すべきは遺言書です。通常であれば遺言書とともに財産目録があり、それを見ることによって遺産の総額を確定することが可能になります。しかし遺言書を遺していないケースも決して少なくありませんので、そういった場合には法定相続に従って遺産を分割する必要があります。
相続人の確定
遺言書を確認するなどして遺産の内容や総額を確定することができれば、併せて相続人も確定しなければいけません。相続人を確定するための方法としては戸籍謄本を確認することが一般的ですが、配偶者や子どもがいる場合にはほぼ相続人になります。配偶者や子どもがいない場合には兄弟や親が相続人になるなど他にもいくつかのパターンがありますので、専門家に相談して相続人を確定させる必要があります。
相続放棄申述書を作成し家庭裁判所へ提出
相続の放棄をするにあたって、相続人間の合意は必要ありません。複数人相続人がいたとして、個人個人の意思として相続放棄を行うことが可能です。相続放棄においてはマイナスの財産のみを放棄するなどといったことはできませんので、プラスの財産・マイナスの財産を一緒に相続放棄することになります。具体的な手続きとしては相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所へ提出することになります。
照会書を返送する
相続放棄申述書を作成し家庭裁判所へ提出してからしばらく経つと「照会書」が届きます。照会書が届いたら必要事項を記入して返送する必要がありますので、忘れずに確認するようにしましょう。
相続放棄申述受理通知書を受け取る
相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所が相続放棄の申述を正式に受理したことを申述した相続人本人に通知するための書類です。相続放棄の手続きが完了したことを示すものであい、基本的に申述者本人にのみ郵送で送付されることになります。
再建築不可物件の相続放棄の注意点
不動産のみの相続放棄ができない
相続人による相続放棄は特定の財産に限定して行うことはできません。たとえばプラスの財産のみ相続してマイナスの財産のみ相続しないなどのように、選別して相続することはできなくなっています。そのため不動産だけ相続しないようにするなどの手続きもできませんので、相続する場合には対象財産をすべて相続する必要がありますので注意が必要です。
手続きは3ヶ月以内に行なう
相続手続きは原則相続の開始があったことを知ってから3か月以内に行わなければいけません。しかしこの3か月以内にすべき手続きというのは「承認または放棄」を意味するものであることに注意が必要です。特に相続放棄はこの3か月以内という期限を過ぎると手続きできなくなり、相続を承認したものとみなされていまいます。
相続財産管理人が決まるまで不動産の管理が必要
相続財産管理人が決まるまでの間は、相続放棄をした場合であっても不動産の管理責任は相続人に残ることとなります。相続放棄をしたからといってすぐに管理義務がなくなるわけではありませんので注意しましょう。相続財産管理人が選任されるまでは、相続人が財産を適切に管理する必要があります。
相続放棄以外に考えられる
対処法
売却する
相続放棄できない・したくない場合、再建築不可物件の売却も検討してみましょう。ただ、リスクの多い再建築不可物件は、需要が限られることで資産価値が低くなりやすく、一般的な不動産では買取を断られることも。
そのようなときは再建築不可物件など"訳あり"不動産の買取を得意としている会社へ相談してみるとよいでしょう。
不動産売却であれば、プラスの財産まで相続を放棄する必要がありません。また不動産の管理義務がなくなるほか、固定資産税や維持費など経済的な負担も軽減できます。
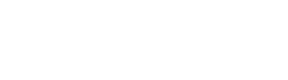 訳あり物件のプロが
訳あり物件のプロが厄介な物件の対処法を解説
このサイトでは相続放棄(拒否)したい理由から、適切な解決策を訳あり物件のプロが解説しています。解説してくれるのは、東京で45年以上買取事業を中心とした不動産業を経営している翔栄の代表 原田氏。一般的には不動産会社に買取を断られるような物件においても高額買取を実施しています。
厄介な物件を相続して困っている方は合わせてチェックしてみてください。
原田 芳史 氏
寄付する
再建築不可物件でも、一定の条件を満たせば寄付という選択肢もあります。
自治体に寄付
公共施設の建設や地域開発の用途に合えば、自治体が引き取る可能性があります。ただし、維持管理の負担が大きいため、ほとんどの自治体では受け入れが難しいのが現状です。
NPOや法人に寄付
地域活性化や文化財保護のために、土地を活用したい団体や法人が引き取ることがあります。興味のある団体を探して相談してみるのもひとつの方法です。
賃貸物件として活用
売却が難しい場合、賃貸として収益化することも考えられます。
倉庫・事務所として貸し出す
物件の立地によっては、倉庫や事務所としての需要があります。特に、トラックの駐車スペースや作業場として活用できる地域では有効です。
駐車場や貸地として運用
土地をそのまま駐車場や貸地として活用し、定期的な収益を得る方法もあります。
任意売却
任意売却とは、住宅ローンの支払いが困難になった場合に、金融機関(債権者)と合意のうえで不動産を売却する方法です。再建築不可物件の場合でも、以下の条件を満たせば任意売却が可能になります。
住宅ローンの残債がある
ローンが残っている場合、金融機関の承諾を得ることで任意売却が可能になります。
買い手が見つかる
通常の売却が難しいため、再建築不可物件を専門に扱う業者や、土地活用を検討している投資家をターゲットにすることが重要です。
まとめ:再建築不可物件を
相続した場合の対処法
再建築不可物件とは、建て替えや増築ができない不動産を指し、特に古い建物ではこの問題が発生しやすい特徴があります。相続した際には、建物の老朽化や管理負担、固定資産税の増加といったリスクを考慮し、早めの対応が必要です。
再建築不可物件を手放す方法として、相続放棄(拒否)の他に、売却、寄付、賃貸物件としての活用、任意売却の検討が選択肢となります。
自分に合った方法を選び、できるだけ早く対応するようにしましょう。
また、このサイトでは相続放棄(拒否)したい理由から、適切な解決策を訳あり物件のプロが解説しています。厄介な物件を相続して困っている方は合わせてチェックしてみてください。

