借地権の相続放棄
借地権は土地を借りて建物を所有する権利です。この記事では、底地権との違いを確認し、借地権を相続放棄する流れやメリット・デメリットについて解説します。
借地権・底地権とは

借地権とは
借地権は、住宅や店舗などを建てることを目的として、地主から土地を借り受ける権利をいいます。契約更新が必要な普通借地権と、更新不要な定期借地権の2種類に区分されています。
借地権は経済価値のある財産とみなされるため相続の対象です。故人(被相続人)が有効性ある借地権を保有していた場合、相続人がその権利を引き継ぐことになります。ただし相続によるトラブルも考えられるため、相続した借地権の取り扱いには注意が求められます。
底地権とは
借地権が設定された土地の所有権を指します。相続時には、借地人との契約や土地の管理が必要になるため、相続後の対応を誤るとトラブルにつながる可能性があるため、慎重な対応が求められます。
借地権・底地権は権利が複雑になり、相続には以下のようなリスクが伴います。
借地権を相続放棄する手続きと流れ
借地権の相続放棄は、家庭裁判所へ申し立て手続きをして行います。申し立てを行うのは、故人(被相続人)が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所です。具体的な手続きの流れを見ていきましょう。
STEP1:必要書類を用意、提出する
相続放棄手続きのために、次の書類を用意しましょう。
- 被相続人の住民票の除票(戸籍附票)
- 申述者の戸籍謄本
- 被相続人の死亡記載がある戸籍謄本(配偶者や子どもが相続するとき)
- 収入印紙800円(手数料)
- 切手(所管の家庭裁判所で異なる)
相続人と被相続人との間柄によっては必要書類が増えることもあります。その場合は家庭裁判所から連絡がくるので、用意して提出するようにしてください。
STEP2:照会書が届き、返送する
申述後、2週間程度で照会書が届きます。照会書には相続開始日や相続放棄の理由などについて質問がありますので、質問事項に記入の上で返送してください。
STEP3:相続放棄手続きが完了する
照会書を返送後2カ月ほど審査がかかりますが、無事に相続放棄手続きがすべて完了すると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これで手続きは完了です。
借地権相続のリスク
借地権を相続することによるリスクは主に3つあります。
相続税が発生する場合がある
特に注意したいのは相続税です。借地権は土地の利活用が可能な権利なため、一定の経済的な価値を持つ財産と判断されます。相続税の対象となりますので、適切に相続税評価を行わなくてはいけません。もし借地権の相続税評価・申告を怠った場合、追徴課税される可能性があります。
借地料が値上げされるリスクがある
借地権を相続した場合、地主に使用料(借地料)を値上げされるリスクも潜んでいます。特に周辺地域と比較して安く借りている場合、地代等増減請求権によって適切な水準まで値上げされる可能性があります。もし値上げを要請された時は、地主と話し合い、適切な借地料を支払うことが重要です。
相続人同士のトラブルになることもある
相続人同士のトラブルにも注意が必要です。借地権を相続すると、相続人は対象の土地を利活用する権利を得ます。一方、土地によっては大きな利益をもたらしますので、遺産分割協議で揉めるおそれがあります。分割して相続する手段もありますが、トラブルにならないよう入念な話し合いが求められます。
借地権を相続放棄するメリット
費用負担が軽くなる
借地権の相続を放棄すると、様々な費用負担を軽減することができます。
- 地代:土地の借地権者ではなくなることから、地主に地代を支払う必要がなくなる
- 固定資産税:土地を所有していることによる固定資産税支払いがなくなる
- 相続税:相続税の対象となる借地権を手放すことで、相続税を払う必要がなくなる
- 解体費用:借地の建物を管理する義務がなくなるため、尺事情の建物を解体する費用を支払わなくて良くなる
- 更新料:借地権を手放すことで更新料を支払う必要がなくなる
管理の手間がかからなくなる
借地権付きの建物を使わない場合、持っているだけで管理するのは大きな手間となります。管理会社に委託することもできますが、手数料を支払わなければいけません。借地権を相続放棄することで、管理の手間がなくなり、活用や売却などの手続きも考えずに済みます。
地主とのトラブルを避けられる
借地権を相続した場合、地代の値上げや立ち退き、建物増改築や売却を認めないなど地主と様々なトラブルが起こる可能性があります。相続を放棄すればこれらのトラブルを回避することができます。
借地権を相続放棄するデメリット
他の遺産も相続できなくなる
借地権の相続を放棄すると、そのほかの財産(預金や不動産など)も全て放棄しなければいけません。利益が得られるはずのプラスの財産まで手放すことになってしまうため、相続放棄前に確認しておきましょう。
ほかの相続人とトラブルになる恐れがある
相続権は高順位の相続人に引き継がれるため、相続を放棄すると次の順位の相続人が借地権を含むすべての財産を引き継ぐことになります。事前に相続を放棄することを伝えなければトラブルになる可能性があるため、相続放棄をする場合は事前に親族に相談しておくことが大切です。
相続人全員が借地権を相続放棄したら
相続人全員が借地権を相続放棄した場合、建物を管理する人がいなくなってしまいます。そのときは、地主が所有者不明建物管理制度を利用することになります。裁判所が所有者不明建物管理人を選任し、裁判所の許可を得て裁判所を管理するものです。
ただし、この手続きはあくまでも相続人がすべて相続放棄をして所有者がいないときに合法的に建物を解体できる制度でしかありません。解体費用を所有者不明建物管理人に請求することはできず、地主が自腹で支払うしかないのです。地主から色々と請求されることがあるかもしれませんが、相続放棄が完了していれば基本的には無視して大丈夫です。何も気にせず、対応してください。
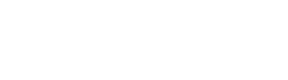 訳あり物件のプロが
訳あり物件のプロが厄介な物件の対処法を解説
このサイトでは相続放棄(拒否)したい理由から、適切な解決策を訳あり物件のプロが解説しています。解説してくれるのは、東京で45年以上買取事業を中心とした不動産業を経営している翔栄の代表 原田氏。一般的には不動産会社に買取を断られるような物件においても高額買取を実施しています。
厄介な物件を相続して困っている方は合わせてチェックしてみてください。
原田 芳史 氏
相続放棄以外に考えられる対処法
地主への買取を請求する
地主に買い取ってもらうことも検討しましょう。相続放棄をして相続人がいなくなってしまうと、相続財産清算人を選任してもらって建物の解体などを行うことになりますが、この時の費用は地主負担となってしまいます。地主にとってもリスクとなるため、相続放棄を検討していることを伝えて買取を打診した方が、地主としても借地権のある土地を取り戻せるため双方にとってメリットがある場合もあります。
第三者へ売却する
地主ではない第三者に売却することができれば、借地権契約を修了させることができます。地主と協力して土地と建物をセットで売ることもできますので、地主と相談してみると良いでしょう。
家族信託を利用する
地主が承諾すれば、借地権を家族信託することができます。委託者が元気なときから家族信託を利用できますから、認知症などにより判断能力が低下した時でも不動産管理や活用ができるように備えられますし、不動産の売却や運用がやりやすくなります。承諾料が発生する可能性もありますが、家族信託は地主にとってもメリットがあるため承諾料が発生しないケースもあります。
まとめ:借地権の相続放棄のポイント
借地権の相続放棄をすると、借地権だけでなくすべての財産を放棄することになるため、プラスの財産がある場合でも相続できなくなってしまいます。借地権だけ放棄することはできませんし、借地権の相続放棄はトラブルが多いのも事実です。
相続後のトラブルを防止するためには、早めに専門家に相談をして適切な対処を選ぶことが大切です。信頼できるプロに相談するようにしましょう。
また、このサイトでは相続放棄(拒否)したい理由から、適切な解決策を訳あり物件のプロが解説しています。厄介な物件を相続して困っている方は合わせてチェックしてみてください。

