空き家の相続拒否
空き家を相続した場合、修繕・メンテナンスなどの維持管理負担が増えるほか、固定資産税も課税されます。ここでは、空き家を相続するリスクや相続放棄の流れ、注意点について解説します。
そもそも空き家とは

空き家は、一定期間以上誰も住んでいないか、使用されていない状態の住宅を指します。少子高齢化が進んでいる日本では空き家が問題になっており、今後さらに増加すると考えられています。
空き家は相続が発生することも珍しくない不動産です。しかし、相続によるリスクも多いため、取り扱いには慎重な判断が求められます。
空き家相続のリスク
空き家の相続には以下のリスクがあります。
維持管理の負担が増える
空き家を相続した場合、管理責任が生じるため維持管理の負担が増加します。建物の定期的な点検はもちろん、保全や修理・修繕を行わなくてはいけません。一方、管理を怠ると倒壊の危険が高まり、隣家に損害を与えるおそれがあります。侵入も容易になるため、放火・窃盗などの犯罪被害に遭うリスクも高まります。
空き家は劣化が早く、屋根や壁、床などの建物本体はもちろん、水回りや外構も老朽化していることがほとんどです。また、カビやシロアリの被害のほか、雨風にさらされているため、構造自体がもろくなり、特に締め切った状態ではさらに劣化が進みます。排水溝からのにおいがきつくなり、においの敏感な方には辛い状況です。
これらを維持・管理しなくてはなりません。
固定資産税の支払いが必要になる
空き家には固定資産税が課税されます。誰も住んでいない・使い道がないなどの理由に関わらず、支払いが必要になることに注意しましょう。固定資産税は、空き家を所有し続ける限り毎年課税されます。
維持管理費用もかかるため、経済的な負担の増加には注意が必要です。
相続人同士でトラブルになるリスク
空き家を複数人で相続した場合、管理責任や固定資産税を逃れるために、相続人同士でトラブルになる可能性もあります。
特に使い道がない物件の場合、責任の押し付け合いになることも考えられます。空き家を複数人で相続した時は、相続人同士で話し合い、責任を明確にすることが大切です。
放置すると行政指導されることも
空き家の管理を放置した場合、自治体の行政指導が入る場合もあります。行政指導は段階的に実施されますが、指導に従わないと行政代執行により解体される可能性も否定できません。なお、行政代執行による解体費用は全額所有者負担となります。
空き家を
相続放棄する場合の流れ
空き家は、以下の手順で相続放棄することも可能です。ただしデメリットが多いため、あくまで最後の手段と考えておきましょう。
- 戸籍謄本などの書類を集める
- 相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に提出する
- 家庭裁判所から届く照会書を記入・返送する
- 相続放棄申述受理通知書を受け取る
まずは書類を集め、次に家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出します。その後に届く照会書を返送し、相続放棄申述受理通知書を受け取れば相続放棄が完了します。
空き家の相続放棄の注意点
空き家を相続放棄する際は以下の点に注意が必要です。
- プラスの財産も相続放棄しなければいけない
- いかなる場合でも取り消しが不可能
- 占有している場合は管理責任が残ることがある
相続放棄を行う場合、現金や貴金属など価値のある他の財産の相続も放棄しなくてはいけません。相続放棄の決定は取り消せないため、全相続財産と引き換えに空き家を手放すことになります。
空き家で占有している部分があると、管理責任が生じることも少なくありません。倒壊などによって被害が出た場合、損害賠償を請求される可能性があります。
相続放棄以外に考えられる
対処法
売却する
空き家の取り扱い方法で迷った場合、売却も視野に入れてみましょう。空き家売却後は維持管理が不要になるため、管理責任を問われる心配もありません。固定資産税の支払いもなくなるほか、現金化することで相続人同士のトラブルも回避できます。
ただし、空き家を売却する際は不動産会社選びが重要です。空き家の買取や売却実績が豊富で、空き家問題に強い不動産会社に相談しましょう。
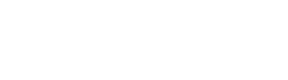 訳あり物件のプロが
訳あり物件のプロが厄介な物件の対処法を解説
このサイトでは相続放棄(拒否)したい理由から、適切な解決策を訳あり物件のプロが解説しています。解説してくれるのは、東京で45年以上買取事業を中心とした不動産業を経営している翔栄の代表 原田氏。一般的には不動産会社に買取を断られるような物件においても高額買取を実施しています。
厄介な物件を相続して困っている方は合わせてチェックしてみてください。
原田 芳史 氏
更地にして売却する
築年数が古く、建物の状態が悪い場合、解体して更地として売却する方法もあります。老朽化した建物があると売れにくいため、更地にすることで売却の可能性が高まることも。
ただし、解体費用がかかるため、土地の価値と費用のバランスを考えて判断することが重要です。
賃貸物件として活用する
賃貸住宅として貸し出す
空き家をリフォームし、賃貸物件として運用することで安定した家賃収入を得られます。
ただし、老朽化が進んだ空き家は修繕費用も膨大になるため、バランスを見た判断が求められます。
駐車場や倉庫として活用
建物の活用が難しい場合、トランクルームや一度更地にしてから駐車場として貸し出すことも考えられます。いずれにせよ建物の修繕、もしくは解体費用が必要となるため慎重な決断をしましょう。
寄付する
再建築不可物件でも、一定の条件を満たせば寄付という選択肢もあります。
自治体に寄付
公共施設の建設や地域開発の用途に合えば、自治体が引き取る可能性があります。ただし、維持管理の負担が大きいため、ほとんどの自治体では受け入れが難しいのが現状です。
受け入れてくれるものとしては、防災倉庫置場、ポケットパーク(住宅街の小規模な公園)、住民の交流場所として活用ができるものが主です。
NPOや法人に寄付
地域活性化や文化財保護のために、土地を活用したい団体や法人が引き取ることがあります。興味のある団体を探して相談してみるのもひとつの方法です。
まとめ:空き家を
相続した場合の対処法
空き家を相続すると、維持管理の手間や固定資産税の負担、老朽化によるトラブルなど、多くのリスクが発生します。管理を怠ると行政指導の対象となる可能性もあり、適切な対処が必要です。相続放棄は一つの手段ですが、現金や他の財産も放棄することになり、撤回もできないため慎重な判断が求められます。
相続放棄以外の対処法としては、売却やリフォームして賃貸物件として活用、駐車場や倉庫として貸し出すことで収益化を図ることが可能です。空き家の管理や処分に悩んだら、早めに不動産会社や専門家に相談し、適切な方法を検討することが重要です。
また、このサイトでは相続放棄(拒否)したい理由から、適切な解決策を訳あり物件のプロが解説しています。厄介な物件を相続して困っている方は合わせてチェックしてみてください。

