立ち退きが必要な物件の相続放棄
老朽化して危険なアパートなど、立ち退きが必要な物件を相続した場合、賃借人との立ち退き交渉が求められます。ここでは、立ち退きが必要な物件を相続するリスクや、相続放棄の流れ・注意点などを解説します。
立ち退きが必要な物件とは
どんな物件?

立ち退きが必要な物件は、主に老朽化で建て替えが必要だったり、諸事情で取り壊しが求められたりする物件が該当します。例えば、老朽化したアパート・マンションを建て替える場合、入居者(賃借人)に立ち退きを要求する必要があります。また、賃貸物件を更地にして売却したい、店舗など別の用途に転用したい、などのケースも当てはまります。
もし賃借人がいる物件を建て替え・撤去したい場合、立ち退き交渉が求められます。しかし、立ち退き交渉からトラブルに発展するリスクもあるため注意が必要です。
立ち退きが必要な物件相続のリスク
立ち退きが必要な物件を相続するリスクは主に3つあります。
賃借人との交渉が必要不可欠
1つめは賃借人との立ち退き交渉です。何らかの事情で物件の建て替えなどを行う場合、賃借人の同意を得なくてはいけません。
法律上、正当な理由なく強制的に立ち退きさせることはできませんので、賃借人とじっくり話し合い、立ち退きに向けたスケジュールを立てたり、物件探しや引っ越しなどをサポートしたりする必要があります。
家賃の滞納や無断転貸といった契約違反は正当な理由となりますが、建物の老朽化による建て替えや売却だけでは、正当な理由として認められないことがあります。
単に売却したいという理由だけでは、正当事由としては認められず、借り手がそのまま住み続ける可能性もあります。また、トラブルが発生すると長期化し、裁判にまで発展する場合もあります。
立ち退き料を請求される
可能性がある
2つめは立ち退き料です。賃借人に立ち退きを要求した場合、立ち退き料の支払いが必要になることがあります。
特に物件を貸す側(賃貸人)の都合による立ち退きでは、立ち退き料を支払うケースが一般的です。ただし費用が高額になるリスクもあるため、弁護士など専門家のサポートも受けながら交渉を進める必要があります。
立ち退き交渉が長期化するおそれも
3つめのリスクは立ち退き交渉の長期化です。賃借人が立ち退きに難色を示した場合、建て替えや取り壊しなどが予定より延びるおそれがあります。
特に賃借人と立ち退き料の同意が得られないケースや、退去を拒まれるケースは珍しくありません。立ち退き交渉する際は、長期化も視野に入れて賃借人と話し合いましょう。
立ち退きが必要な物件を
相続放棄する場合の流れ
立ち退きが必要な物件を相続放棄したい時は、以下の流れで手続きを進めましょう。
- 戸籍謄本など相続放棄に必要な書類を揃える
- 相続放棄申述書を作成する
- 相続放棄申述書と書類を家庭裁判所の窓口に提出する
- 照会書を確認して再送する
- 相続放棄申述受理通知書を受け取る
書類を家庭裁判所へ提出し、後日届く照会書を返送することで、相続放棄に関する審査が行われます。審査後、内容に問題がなければ相続放棄が受理されます。
ただし、相続放棄はさまざまなリスクを伴います。あくまでも最終手段のため、別の方法も検討することが大切です。
相続放棄の注意点
相続放棄には以下のリスクがあります。
- 現預金などプラスの財産も相続できない
- 物件を手放すまでは管理義務が生じる
- 相続放棄を取り消しできない
相続放棄後は、相続した財産に現預金などのプラス財産があったとしても相続できません。相続放棄は、全財産の相続権を放棄する手続きだからです。
また、相続放棄を行ったとしても、物件の新しい管理者が見つかるまでは管理義務が生じます。相続放棄の決定は撤回できませんので、相続放棄申述書の提出可否は慎重に判断しましょう。
相続放棄以外に考えられる
対処法
売却する
立ち退きが必要な物件を手放したい場合、不動産会社に売却してみてはいかがでしょうか。不動産売却であれば相続放棄の必要がなく、プラスの財産も相続可能です。立ち退き交渉も不要なため、交渉に伴う精神的・金銭的負担も軽減できます。
立ち退きが必要な物件を相続した場合、速やかな対応が求められます。しかし相続放棄はリスクが大きいため、迷った際は不動産売却をおすすめします。
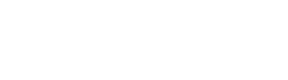 訳あり物件のプロが
訳あり物件のプロが厄介な物件の対処法を解説
このサイトでは相続放棄(拒否)したい理由から、適切な解決策を訳あり物件のプロが解説しています。解説してくれるのは、東京で45年以上買取事業を中心とした不動産業を経営している翔栄の代表 原田氏。一般的には不動産会社に買取を断られるような物件においても高額買取を実施しています。
厄介な物件を相続して困っている方は合わせてチェックしてみてください。
原田 芳史 氏
賃貸物件として継続運用する
そのまま賃貸物件として継続運用する方法もあります。立ち退きをせず、借主が引き続き入居することで、家賃収入を得ることができるため、経済的な負担を軽減できます。
ただし、管理の手間がかかるため、物件の管理が難しい場合は、賃貸管理会社に委託することで運営の負担を減らすことができます。
共有者や親族に譲渡する
相続人が複数いる場合や、家族の中に物件を活用したい人がいる場合、売却ではなく譲渡する方法もあります。
共有者の中で物件を活用したい人がいれば、持分を売却するか無償で譲ることも可能です。また、親族に贈与することで手放すこともできますが、贈与税が発生する可能性があるため、税理士に相談しながら進めることをおすすめします。
まとめ:
立ち退きが必要な物件の
相続リスクと対処法
立ち退きが必要な物件を相続すると、賃借人との交渉や立ち退き料の負担、交渉の長期化などのリスクが発生します。相続放棄を選ぶと他の財産も放棄することになり、一度放棄すると撤回できないため慎重な判断が必要です。
賃貸物件として継続運用することも可能ですが、管理の負担が増えるため、専門の管理会社に委託するのが望ましいでしょう。
立ち退きが必要な物件を相続した場合は、早めに専門家に相談し、適切な方法を選ぶことが重要です。
また、このサイトでは相続放棄(拒否)したい理由から、適切な解決策を訳あり物件のプロが解説しています。厄介な物件を相続して困っている方は合わせてチェックしてみてください。

