古アパートの相続放棄
古アパートを相続した場合、維持管理の手間が増えるほか、空室などのリスクに対処しなくてはいけません。ここでは、古アパートを相続するリスクや、相続放棄する方法や注意点をご紹介します。
古アパートの基準は?

古アパートの基準は、主に「築年数」「耐震基準」の2点から判断されます。
築年数の目安は、築20年以上の物件を「古アパート」と判断することが一般的です。法定耐用年数は、木造アパートが22年、鉄骨造は27〜34年、鉄筋コンクリート造は47年です。以上から、築30年、50年の物件は、建て替えまたは大規模修繕の検討が必要です。
また「耐震基準」については、建物がいつ建てられたかが重要なポイントです。1981年6月1日以前に建築確認を受けた物件は「旧耐震基準」で建てられていますが、それ以降の物件は「新耐震基準」に適合しているため震度6〜7に耐えられる設計となっています
以上から木造アパートは築22年以上、鉄筋コンクリート造は築47年を経過している場合には、法定耐用年数を超えており、さらに1981年の新耐震基準以前に建てられたものは、旧耐震基準物件として区別されます。また、古い物件は家賃が安く利回りが高いものの、修繕費が高額となるリスクも考えられます。
古アパート相続で資産が負債に変わるリスクについて
古いアパートを相続する際には、いくつかの注意点があります。たとえば、相続税がかかることや、建物の修繕・管理に費用や手間がかかることなどです。こうした負担をあらかじめ理解したうえで、資金の準備や対策を考えておくことが大切です。場合によっては、売却も含めて、今後どう運営していくかをしっかり検討しておきましょう。
相続税の計算方法に注意
特に気を付けておきたいのは相続税です。アパートなどの賃貸物件は、部屋の稼働率と稼働面積の割合(賃貸割合)が相続税評価に影響します。賃貸割合が高いほど相続税の負担が減るため、空室が常態化している物件は相続税が高くなるおそれがあります。
維持管理の負担が増える
古アパートを相続した場合、物件の継続的な維持管理が求められます。しかし外壁や屋根の塗装、設備の修理や更新、改修などの維持管理には費用が必要です。
安定した賃料収入があれば問題ありませんが、赤字経営の場合は経済的な負担が発生します。
空室リスクが高い
古アパートはニーズが少ないため、新築物件や築浅物件と比較して空室リスクが高めです。地域の賃貸需要にもよりますが、一度空室が発生した場合、入居者が中々見つからない可能性もあります。
空室リスクを減らすには、リフォーム・リノベーションを行うなどして物件に付加価値を与える必要があります。
賃料下落のリスクも
賃料の下落にも注意が必要です。古アパートは設備が古いため、入居希望者も限られてしまうのが実情です。
入居者を増やすためには、先述のリフォームを行うか、周辺物件よりも安い家賃で貸し出すなどの工夫が求められます。ただし収益性が下がるため、赤字経営になる可能性が高まります。
賃貸としている場合は確定申告が必要
賃貸経営を継続する場合、家賃収入が発生するため、毎年の確定申告が必要となります。特に、相続人が不動産運営の経験がない場合、手続きの煩雑さが大きな負担となることがあります。
複数の相続人がいる場合トラブルが発生しやすい
古アパートに複数の相続人がいる場合には、相続に関して意見がまとまらず、トラブルが発生する可能性が高いといえます。例えば、あまりにも古い物件である場合やアパートの経営を行うのが難しいなどの理由で手放したいと考えることもあるでしょう。しかし売却などを行う場合には、相続人全員の承諾が必要となります。人数が少ない場合には意見もまとまりやすいものの、古いアパートの場合相続が繰り返されており、相続人も複雑になっている可能性もあります。
このような場合には、早い段階で相続人全員で話し合いを行い、トラブルを避けるための対策を講じることが大切です。
負債を抱えるリスク
アパートを引き継いだとしても、それまで賃貸管理の経験がない場合にはどのように対応していけば良いかわからない可能性もあります。
もしアパートの管理や経営ノウハウが全くない、ノウハウを引き継いでいないといった場合には、経営がうまくいかず安定した家賃収入を得るのが難しくなってしまい、逆に負債を抱えてしまうリスクも考えられます。
耐震補強が必要なケースもある
古い建物の場合、「旧耐震基準」で建てられている可能性があります。具体的には、1981年6月1日以前に建築確認を受けている物件であれば、「旧耐震基準」で設計されています。この旧耐震基準は、震度5程度に耐えるレベルとされています。
現在は震度6~7程度に耐える設計の「新耐震基準」で建築が行われていることからも、古い建物の場合には耐震補強が必要になるケースがあります。当然ながら、補強を行う場合にはその分のコストが発生します。
孤独死や事故のリスク
古いアパートには、昔から長く住んでいる人もいるかもしれません。もし入居者が高齢である場合には、部屋の中で孤独死や事故が発生してしまうリスクが高くなるといえます。そのため、日頃から入居者の様子に気を配ったり、コミュニケーションを増やすことが大切です。また、入居者の安否確認を行う見守りサービスを導入するといった対策も考えられます。そのほかにも、孤独死保険といったものを活用するのも対策のひとつであるといえます。
追加の税負担の可能性
もし古アパートを売却すると決めた場合、負担しなければならない税金が発生する点はあらかじめ念頭に置いておくことが大切です。不動産を売却した場合には「譲渡所得税」と呼ばれる税金が発生します。これは、売却によって利益が発生した場合に課せられる税金で、復興特別所得税を含む所得税と住民税の合算となっています。
さらに、譲渡所得税の税率は売却した不動産の所有期間により変わってきます。不動産を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合には「長期譲渡所得」とみなされ、税率は約20%となります(ちなみに、所有期間が5年以下(短期譲渡所得)の場合は、税率が約39%と設定されています)。
古アパートを相続放棄する
場合の流れ
もし古アパートを相続放棄したい時は、以下の手順で手続きが可能です。ただしデメリットも多いため、慎重な判断が求められます。
- 戸籍謄本など相続放棄に必要な書類を集める
- 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する
- 家庭裁判所から届く照会書を確認・記入する
- 照会書を返送する
- 相続放棄申述受理通知書を受け取る
必要な書類を集め、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しましょう。その後届く照会書を返送し、相続放棄申述受理通知書を受け取れば完了です。
古アパートの相続放棄の
注意点
相続放棄には以下のデメリットがあります。
- 預金や他の不動産なども相続放棄が必要
- 財産を処分した場合は相続放棄できないことがある
- 確定後は撤回できない
- 他の相続人の負担が増える
相続放棄を行った場合、預金や不動産など価値ある財産も相続できません。プラスとなる財産は他の相続人が相続することになります。一方、相続財産を一部でも処分した場合、単純承認とみなされ相続放棄できないケースがあります。
また、相続放棄は撤回が不可能で、他の相続人の負担増加に繋がります。後々トラブルとなる可能性もありますので、相続放棄以外の手段も検討しましょう。
相続放棄を行う場合、相続開始と自己の相続人となったことを知ってから原則3ヶ月以内に相続放棄の申述を行わなければならない、という法的な期限が定められている点に注意が必要です。また相続放棄をしたとしても、相続財産の管理責任が一時的に残るケースもあるため、速やかに対応を行ってください。
さらに、価値ある残置物を無断で持ち出した場合には、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ「単純承認」とみなされ、相続放棄が認められなくなるというリスクがある、という点もあらかじめ知っておくことが大切です。
相続放棄以外に考えられる
対処法
物件を更地にして売却する
老朽化したアパートは買い手がつきにくいため、解体して更地として売却する方法もあります。ただし、解体費用が発生するため、土地の価値とのバランスを考えて判断する必要があります。
親族に譲渡する
相続人以外の親族にアパートを贈与することも一つの手段です。ただし、贈与税が発生する可能性があるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
建て替え・リフォームを行う
古アパートを新しい建物に更新することによって、収益性を高められる可能性があります。また、修繕やリフォームを行えば建物の寿命を伸ばせるため、賃貸需要の改善を狙うことが可能となります。
生前贈与や資産組み換え
古アパートを所有している親が存命の場合には、生前贈与や資産の組み換えを行う方法も考えられます。遺産として古アパートを相続した場合には、建物や土地の価値によっては数百万円近くの相続税がかかるケースもあります。このような場合、あらかじめ生前贈与や資産の組み換えを行っておくことにより、財産を相続した人の負担の軽減に繋げられるというメリットがあります。
遺産分割協議による相続分放棄
遺産分割協議による相続分の放棄とは、他の相続人に対して相続分を放棄する旨を主張し、相続人同士で話し合って合意すれば相続放棄を行えます。遺産分割協議で相続分を放棄する場合には、家庭裁判所での手続きは不要です。そのため古アパートの相続に関し、家族間で遺産の分割について調整を行い特定の相続人がアパートを引き継がない、といったことも可能になります。
ただし法的な相続放棄とは異なり、遺産分割協議では債務を免れることはできない点には注意してください。
売却する
古アパートの取り扱いで迷った時は、不動産売却をおすすめします。不動産売却であれば、預金などプラスの財産の相続を放棄する必要がありません。他の相続人の負担軽減にも繋がるため、相続人同士で一度話し合ってみてはいかがでしょうか。
ただし、古アパートの売却は不動産会社選びが大切です。相続不動産の取り扱いが得意な会社や、築古物件の取引実績が豊富な会社に相談しましょう。
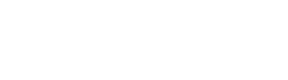 訳あり物件のプロが
訳あり物件のプロが厄介な物件の対処法を解説
このサイトでは相続放棄(拒否)したい理由から、適切な解決策を訳あり物件のプロが解説しています。解説してくれるのは、東京で45年以上買取事業を中心とした不動産業を経営している翔栄の代表 原田氏。一般的には不動産会社に買取を断られるような物件においても高額買取を実施しています。
厄介な物件を相続して困っている方は合わせてチェックしてみてください。
原田 芳史 氏
まとめ:
古アパートを相続した際の
リスクと対処法
古アパートを相続すると、維持管理の負担、空室リスク、確定申告の義務など、多くの壁が立ちはだかります。相続税の計算方法によっては、思わぬ税負担が発生する可能性もあるため注意が必要です。
相続を望まない場合は、売却したり、親族に譲渡するなどして早めに対処するのが良いでしょう。相続放棄も可能ですが、預金など他の財産も放棄する必要があるため、慎重な判断が求められます。
古アパートの扱いに悩んだら、早めに不動産の専門家や税理士に相談し、適切な方法を検討することが大切です。
また、このサイトでは相続放棄(拒否)したい理由から、適切な解決策を訳あり物件のプロが解説しています。厄介な物件を相続して困っている方は合わせてチェックしてみてください。

