築古物件の相続放棄
築年数がかさんだ築古(ちくふる)物件は、相続するリスクも決して小さくありません。そのため相続放棄を選ぶケースも見られますが、相続放棄以外の手段も検討する価値があります。
築古物件の定義は?

築古物件は、築年数が30年程度経っている古い建物をいいます。建築から相応の時間が経過しているため、法定耐用年数を超えているケースもあります。
築古物件は住宅性能が低く、設備も古くなっていることも珍しくありません。築浅物件と比べ、維持管理費用が高額になる可能性があります。
築古物件相続のリスク
築古物件を相続する場合、以下のリスクには注意が必要です。
毎年固定資産税が課税される
築古物件を相続した場合、毎年固定資産税を支払わなくてはいけません。物件の価値によっては、毎年数万円〜数十万円の固定資産税が課税されます。
経済的な負担が増えるため、相続人が複数いる場合は固定資産税の支払いで揉めるリスクもあります。
維持管理の負担が増える
維持管理の負担増加にも注意が必要です。築古物件は全体的に古いため、修繕費用や設備の交換費用が膨らむ傾向があります。こまめな点検も求められますので、体力面の負担も決して小さくありません。
また、住まいと築古物件の場所が離れている場合、交通費が膨らんでしまう可能性もあります。
耐震性や断熱性が低い物件が多い
築古物件は古い基準で建てられている建物が多く、耐震性や断熱性などの住宅性能は低めです。
築古物件に住む場合、現在の住まいより快適性・安全性が低下することも考えられます。耐震・断熱リフォームも費用がかかるため、住み替えが適切とは限りません。
需要が少なく物件の活用が難しい
築古物件はニーズが限られるため、賃貸への転用もリスクを伴います。そのままでは収益性も低いため、赤字になるおそれもあります。
仮に賃貸へ転用する際はリフォーム・リノベーションや、周辺より家賃を安くするなどの対応が必要です。
築古物件を
相続放棄する場合の流れ
築古物件を相続放棄する場合、下記の流れで手続きを行います。
- 相続放棄に必要な書類を集める
- 相続放棄申述書と書類を家庭裁判所に提出する
- 家庭裁判所から届く照会書を記入・返送する
- 相続放棄申述受理通知書を受け取る
家庭裁判所へ相続放棄に必要な書類と申述書を提出すると、後日照会書が届きます。照会書を記入・返送し、相続放棄が完了すると相続放棄申述受理通知書が届きます。
なお、相続人が他にいないか、全員が相続放棄した場合、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が財産を管理・精算します。
築古物件の相続放棄の注意点
相続放棄は以下のリスクを伴うため、必ずしも適切な手段とはいえません。
- 現金・預金や他の不動産も相続できなくなる
- 相続放棄決定後はいかなる手段でも撤回不可能
- 他の相続人の負担が増加する
相続放棄は、現金や預金などプラスとなる財産の相続権も放棄が必要です。築古物件のみ相続放棄、とはいかないことに注意しましょう。また、どのような理由であっても決定を覆すことはできません。後日隠し財産が見つかったとしても相続は不可能です。
相続放棄を行うと、他の相続人に築古物件の相続権が移ります。他の相続人の負担が増えるため、トラブルにならないように注意が必要です。
相続放棄以外に
考えられる対処法
売却する
プラスの財産があるなどの理由で相続放棄が難しい時は、築古物件の売却をおすすめします。築古物件は需要が限られますが、買取に対応している不動産会社もあります。築古物件の取り扱いに困った時は相談してみましょう。
築古物件を買取してもらえば、速やかな現金化が可能です。売却益を相続人同士で分配できるため、相続で揉めるリスクを軽減できます。また、固定資産税の支払いや物件の維持管理も不要です。経済的な負担を減らせるため、相続放棄の前に不動産売却を検討してみましょう。
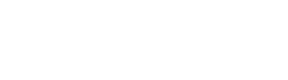 訳あり物件のプロが
訳あり物件のプロが厄介な物件の対処法を解説
このサイトでは相続放棄(拒否)したい理由から、適切な解決策を訳あり物件のプロが解説しています。解説してくれるのは、東京で45年以上買取事業を中心とした不動産業を経営している翔栄の代表 原田氏。一般的には不動産会社に買取を断られるような物件においても高額買取を実施しています。
厄介な物件を相続して困っている方は合わせてチェックしてみてください。
原田 芳史 氏
更地にして売却する
築古物件は建物の価値が低くなるケースも多いため、解体して更地として売却する方法もあります。ただし、解体費用が発生するため、土地の価値と解体費のバランスを考えて判断することが大切です。
親族に譲渡する
相続人以外の親族に物件を贈与することも一つの手段です。ただし、贈与税が発生する可能性があるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
賃貸物件として運用する
築古物件でも賃貸需要があれば、賃貸物件として活用することで収益を得ることができます。管理の負担を軽減するため、賃貸管理会社に運営を委託するのも一つの手段。リフォームやリノベーションを行い、資産価値を向上させることで空室リスクを低減することも可能です。
自治体やNPO法人に寄付
公共利用が見込める場合、自治体が物件を引き取る可能性があります。ただし、管理負担の関係で受け入れが難しいケースも多いため、事前に相談が必要です。
地域活性化や福祉目的で、NPO法人が活用するケースもあるため、受け入れ可能かどうか、各団体に問い合わせてみるとよいでしょう。
まとめ:
築古物件の相続リスクと
対処法のまとめ
築古物件を相続すると、固定資産税の負担、維持管理の手間、耐震性や断熱性の低さ、賃貸需要の低迷といったリスクが伴います。そのため、相続放棄を検討するケースもありますが、売却や譲渡など他の対処法もあります。
放置すると、税金や管理費がかかり続けるため、早めの対策が重要です。売却や譲渡を検討する場合は、不動産会社や専門家に相談し、適切な方法を見つけましょう。
また、このサイトでは相続放棄(拒否)したい理由から、適切な解決策を訳あり物件のプロが解説しています。厄介な物件を相続して困っている方は合わせてチェックしてみてください。

